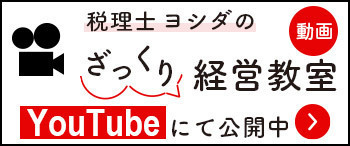新潟市の税務会計は新潟の税理士、会計事務所にご相談ください!
高品質で低価格、腰の低い柔軟な税理士が対応!確定申告や起業支援、会社設立、資金調達(融資、補助金、助成金等)もお任せください!
遺産分割の留意点
遺産分割の際に、どのような点に留意するべきでしょうか?
| 遺産分割に際しては、 相続税の特例の活用や分割後の税負担あるいは相続人の次の世代のことなど、 |
【1】配偶者の税額軽減の特例と二次相続
配偶者の税額軽減の特例を活用すると多くの場合、配偶者については相続税はかかりません。
しかし、二次相続まで考えて遺産分割を考えたいものです。
すなわち、一次相続時点において、相続税をもっとも低くする方法は配偶者の相続分を法定相続割合以上にするか、配偶者の相続財産額を1億6,000万円以上にすればよいのですが、二次相続のときは配偶者の税額軽減の特例は利用できません。
二次相続が近いうちに発生しそうな場合などには、配偶者固有の財産も考慮に入れてシュミレーションすることが必要です。
【2】小規模宅地等の評価減の特徴
小規模宅地等の表加減の適用を受けられる土地が複数ある場合、どの土地に適用を受けるかは相続人にまかされています。したがって、評価減が一番大きくなる土地に優先して適用するようにします。
相続する土地の取得者によって減額割合が異なることもありますし、二次相続の時にも大きく影響しますので、この選択は極めて重要です。
【3】土地の相続と登記
土地を相続人間で共有にすると将来トラブルのもとになることがあります。
被相続人にしてみれば、『子どもたちは仲が良く、相続争いをすることはないだろう』と思うかもしれません。ところが、共有にすることにより、一人ひとりの土地の処分権限は制約されますので、それが原因でトラブルが発生することがあります。
たとえ相続人間はうまく共有関係を維持できたとしても、その子どもたちに相続されると、その土地はいとこ同士で共有することとなってしまいます。そのときはよりトラブルが発生しやすくなります。
このような心配をしなくて済むよう土地は単独所有で相続させるのが良いといえます。
(相続税の納税のための売却予定地や物納予定地については、あえて共有にすることが良いこともありますので、税理士等の専門家に相談してください)
また、1筆の土地を複数の相続人が単独所有で相続するためには、分筆をすることになります。この場合、分筆の仕方によっては相続税評価額が下がる場合もありますので、専門家と相談しながらしたほうがよいでしょう。
なお、登記簿上の地積と実測による地積とは異なることもありますので、分筆するときは、あわせて測量を行うことも必要です。
土地評価にあたっては、地積が登記簿と実測で異なる場合には、当然実測の地積を使います。
【4】代償分割の活用
長男が多くの財産を相続し、その代わり相続税は長男が全て支払う、といった場合によく問題が出てきます。
相続税は各相続人が相続した財産額に応じて支払うべきなのですが、全てをある特定の方が支払った場合は、支払うべき方は長男から金銭の贈与を受けたものとして、贈与税を納めなければなりません。
そこで代償分割を活用して贈与税を負担しなくてすむよう工夫することが必要です。
また、この代償分割は相続人間の不公平感をなくすことにも効果を発揮します。
例えば、ある土地を相続した方は小規模宅地等の評価減を利用したため、不動産の時価では他の相続人と同じ財産の額を相続していても、税額が少ないということがあります。
このようなことによるトラブルも代償分割の活用により回避できます。
代償分割は遺産分割の方法の1つとして、遺産分割協議書に代償分割によって遺産を分割したことを記載しておくことが必要です。
【5】その他の留意点
その他の留意点を簡単にまとめると次のような点が挙げられます。
- 土地の分割取得による土地評価額引き下げ
土地は、原則として各相続人が取得した土地ごとに評価しますので、土地の分割取得を工夫することにより土地の評価額を引き下げることもできます。
- 相続税の納税のため、延納や物納を検討する
- 相続後の財産処分に伴う税負担や各相続人の所得状況などを考慮する
例えば、相続不動産を売却する予定がある場合などにおける譲渡所得税や賃貸マンションを相続した場合に不動産収入など。また、年金生活の配偶者が残された場合は、不動産よりも金銭を相続させるなど。
- 借入金のある賃貸不動産
借入金の利子は不動産所得の必要経費として計上できるため、借入金の承継者と賃貸不動産の承継者を切り離さない。
- 二次相続が近いと思われるとき
金銭など消費するものや将来値下がりする可能性のある財産は配偶者が相続し、値上がりが見込まれる財産は子どもが相続する。
新潟の税理士への無料相談はこちら

お気軽にご相談ください!
オンライン対応も可能です!
営業時間:平日9:00〜17:30
◆新潟市オフィス
950-0941 新潟県新潟市中央区女池4-18-18-2F
℡:025-383-8868
◆三条オフィス
955-0081 新潟県三条市東裏館2-14-15
℡:0256-32-5002